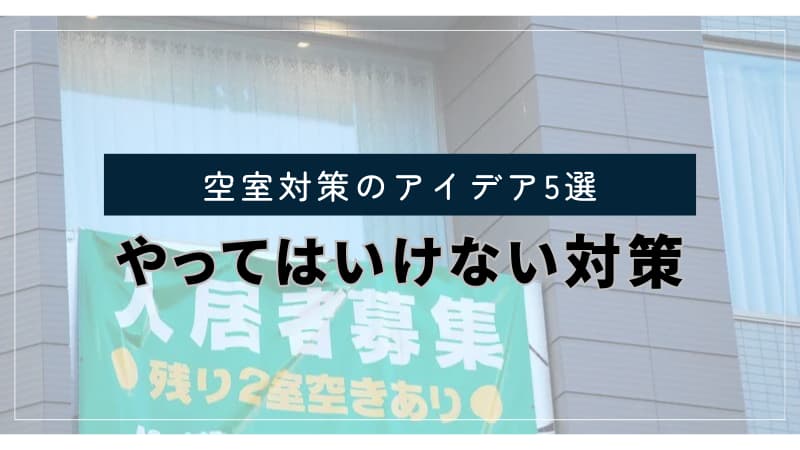
賃貸経営において、空室が発生するといち早く入居者を決めなくては、収益は入ってきません。
では、空室対策にはどのようなものがあるのでしょうか。やってはいけない空室対策についても紹介します。
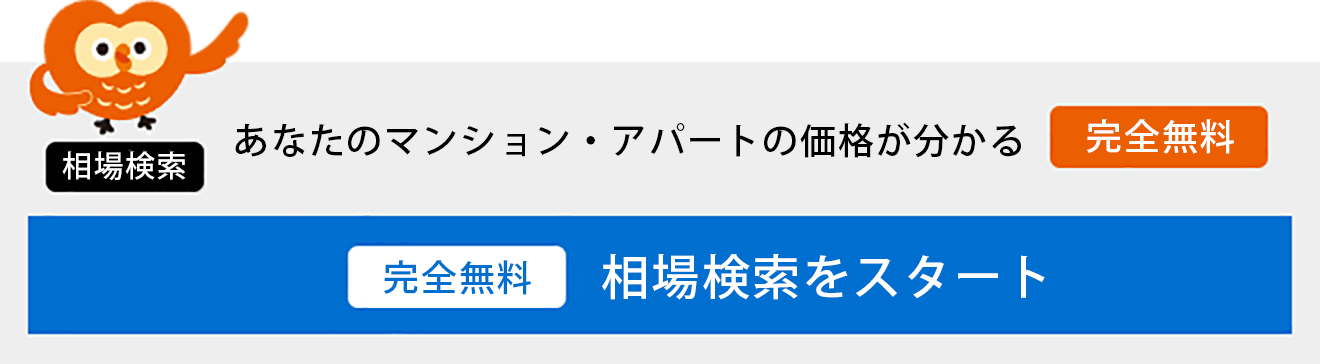
おすすめの空室対策のアイデア5選
賃貸経営をするうえで欠かせないのが空室対策です。空室対策で失敗しないための事前準備や検証事項、具体的な空室対策について解説します。
空室対策で失敗しないために必要なこと
空室対策を失敗しないために、まず次のことに注意しましょう。
市場調査
物件の立地や競合物件の状況、入居者のニーズや嗜好などを把握することで、適切な賃料設定や広告戦略を立てることができます。
費用対効果の分析
空室対策にはコストがかかる場合が多いので、投資した分だけ入居率や家賃収入が上がるかどうかを慎重に検討することが必要です。
効果測定と改善
空室対策を実施した後は、その効果を定期的に測定し、必要に応じて改善策を講じることが必要です。
市場や入居者のニーズは変化するものなので、常に最適な空室対策を追求することが重要です。
以上のことをふまえて賃貸不動産の有効な空室対策を5つ紹介します。
- 不動産会社に広告を出してもらう
- 家賃を下げる
- 敷地内や共用部を清掃する
- 設備投資をする
- 入居者ターゲットを変更する
不動産会社に広告を出してもらう
賃貸物件の入居者を募集する際は、不動産会社の協力を得て広告を出すのが基本です。
不動産の広告としては、新聞や賃貸情報誌、折り込みチラシなどの紙媒体のほか、インターネットのポータルサイトに掲載する方法があります。
広告を見て入居の判断をする人は多いため、掲載方法や内容に問題がないか確認しましょう。
家賃を下げる
値下げをして入居者に経済的メリットを示すのが最もシンプルですぐにできる空室対策です。
ただし、家賃を下げれば収益性は低くなりますし、利回りは下がります。
そのため、周辺地域の家賃相場を調査したうえで相場とかけ離れた賃料にならないように調整することが重要です。
家賃を下げてしまうと、再び値上げするのが難しいケースもあります。
敷地内や共用部を清掃する
建物や敷地内のイメージを向上させるために、敷地内や空室を見回り、清掃を行いましょう。
ゴミが落ちていたり蜘蛛の巣がはっていたりする物件は、それだけで印象が悪いもの。
室内が立派でも外観が汚ければ、入居率はダウンします。
設備投資をする
物件の築年数が古いと、設備や外観が新築物件よりも見劣りするケースがみられ入居者が集まりにくい傾向があります。そのため、リフォームやリノベーションを行って設備や間取りを改善することで、物件の魅力を高められます。
ただし、リフォームには高額な費用がかかるので費用対効果を考えて実施することが大切です。
入居者のターゲットを変更してみる
物件がある地域の利用者のニーズを見極めることが大切です。
単身者が多い地域や学生街ならばワンルームや1Kなどの小さい間取り、ファミリー層が多いならば3LDK以上の大きい間取りが好まれるでしょう。
そのエリアのニーズから最適な間取りは何かを考え、ときには入居者のターゲットを変更する必要があります。
プロがおすすめする空室対策
ファイナンシャル・プランナーによる
みらい収支シミュレーションはこちら
やっていけない空室対策とは
空室対策は、賃貸不動産オーナーにとって重要な課題であり、空室が長期化すると収入が減少し経営に影響が出ます。
しかし、空室対策には逆効果になることもあるので注意しましょう。
以下に、やってはいけない空室対策の例を3つご紹介します。
- 家賃を大幅に下げる
- リフォームにお金をかけすぎる
- むやみな入居条件の緩和
- 管理会社や不動産屋まかせにする
家賃を大幅に下げる
空き室が埋まらないことに焦って家賃を大幅に下げても、根本的な解決にはなりません。
家賃を下げると、入居者の質が低下したり、他の部屋の入居者から不満が出たりする可能性があります。
また、家賃を上げるタイミングも難しくなります。
家賃設定は、地域相場や物件の立地・設備・間取りなどを考慮して適正に行うことが必要です。
リフォームにお金をかけすぎる
リフォームは空き室対策として有効ですが、必要以上にお金をかけるのは良くありません。
リフォーム費用は、家賃アップや入居率アップに見合うものである必要があります。
また、リフォームする場合は、入居者のニーズやトレンドに合わせたものであることが重要です。
たとえば、和室から洋室への変更や、無料インターネットの導入などは効果的です。
しかしながら、余分なお金をかけたくないし、入居者のニーズにあわせようとして、入居者が決まってからリフォームをするのは誤りです。
入居希望者には、リフォーム後のきれいな状態で内見をしてもらうように心がけましょう。
むやみな入居条件の緩和
入居者ターゲットを変更するために入居条件を緩和することは空室対策として有効ですが、むやみに入居条件を緩和することはおすすめしません。
たとえば、今までペット飼育を禁止していたものを解禁すると次のような問題が生じるおそれがあるからです。
- ペットの匂いが室内に残るので退去後の清掃に費用がかかる
- ペットの鳴き声で苦情がでる
- 大きい犬や蛇などに対して他の居住者が恐怖や不安を感じることがある
また、外国人を受け入れるときにも注意が必要です。
- 家賃未納のまま帰国されてしまい、回収不能になるおそれがある
- 言葉や慣習の違いから他の居住者とトラブルになるおそれがある
このように入居条件を緩和するとトラブルになるおそれがあるため、ペット可物件にするときには入居時の原状回復義務の徹底やペット飼育の条件の明確化などが必要になるでしょう。
また外国人を受け入れるときには、家賃保証会社との契約義務化や日本での居住期間や日本語が話せるかの確認、就労先・勤務年数の確認などをしておくとよいでしょう。
管理会社や不動産屋まかせにする
管理会社や不動産屋に丸投げしても、入居者が獲得できるわけではありません。
オーナー自身が物件の状況や市場動向を把握し、積極的に空室対策を打つことが必要です。
また、管理会社や不動産屋とのコミュニケーションも重要です。
信頼できるパートナーを選び、定期的に情報交換や相談を行うことで、より効果的な空室対策ができるでしょう。
管理会社から提案される間違った空室対策とは
はじめての投資マンション売却
こちらから!
長期に渡って埋まらない賃貸物件の対策とは
いろいろな空室対策をとってみたものの長期間空室が埋まらないときには思い切った対策が必要になります。
賃貸経営では出口戦略が大事になるので、場合によっては物件の売却も視野に入れることが大切です。
管理費や駐車場代を「家賃込み」にする
割安感を演出するために管理費や駐車場の代金を「家賃込み」と表示することで入居希望者にアピールできます。
通販でも「送料無料」と表示してあるとお得感がありますよね。
クレジットカード払いにする
家賃をクレジットカード払いできるようにすれば入居者はポイントを得られるメリットがあるので喜ばれます。
家賃は毎月発生するためポイントをためやすく入居者のメリットは大きくなります。
フリーレント期間を設ける
入居後一定期間の家賃を無料にするフリーレントという方法もあります。
敷金や礼金を減額または廃止にするといざというときの保証がなくなるためオーナーの負担が大きくなりますが、一定期間無料のフリーレントだと対応しやすいでしょう。
入居希望者にとって引越費用は大きな負担になるので、数カ月であってもよろこばれます。
スマートホーム化も空室対策として有効
賃貸物件でもスマートホーム化は可能で、比較的安価にできる対策です。
「インターネット無料」「オートロック」「高速インターネット」「防犯カメラ」「ホームセキュリティ」などスマートホーム化で対応できる機能は入居者に人気のある設備なので、競合物件との差別化に効果的です。
出口戦略としての売却
不動産賃貸経営の出口戦略とは、賃貸物件をいつ、どのように手放すかを計画することです。
出口戦略は、賃貸経営の成功にとても重要な要素であり、出口戦略には、大きく分けて「売却」と「保有」の2つの方法があります。
長期間空室が埋まらないための出口戦略なので、売却も検討してみてもよいかもしれません。
売却するタイミングは、物件の価値や需要、保有期間で異なる譲渡所得税の税率などを考慮して決める必要があります。
アパートやマンションといった物件で、築年数が経過している場合には、そのまま売却する場合と、解体して更地にして売却する場合があります。
解体して更地にして売却する場合は、買い手にとっては解体費用がかからないメリットがありますが、解体費用や固定資産税などのコストも考える必要があります。
そのまま売却する場合は、入居者がいる状態でオーナーチェンジ物件として売ることが多く相場より高く売れる可能性がありますが、空室期間が長ければ収益性が低いとみなされ高値での売却が難しい場合もあります。
しかしながら、売却することで一時的に大きな収入を得ることができ管理やリスクから解放されるメリットがあります。
不動産賃貸経営は「投資」であるため、ときには、「勇気ある撤退」や「損切」の選択も必要になるでしょう。
どうしても埋まらない部屋というのはある?
空室に悩まない物件選びのポイントはある?
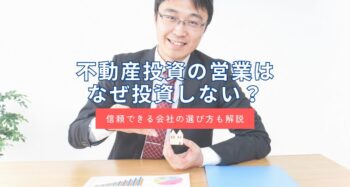




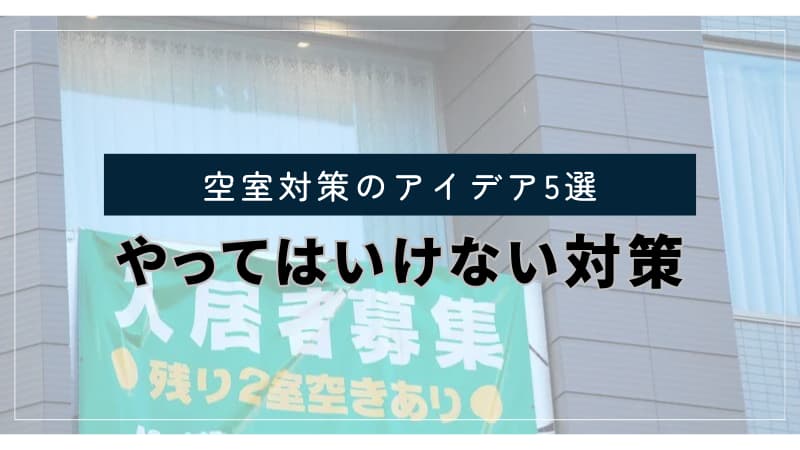
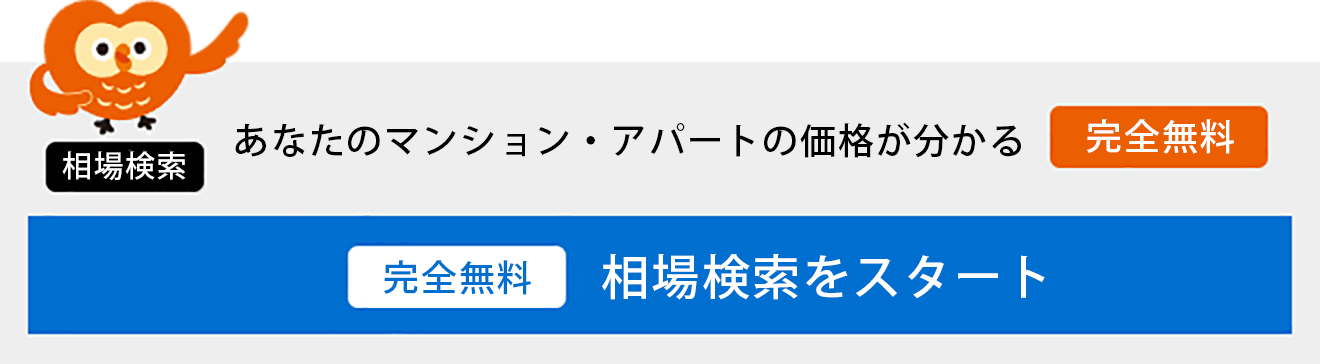


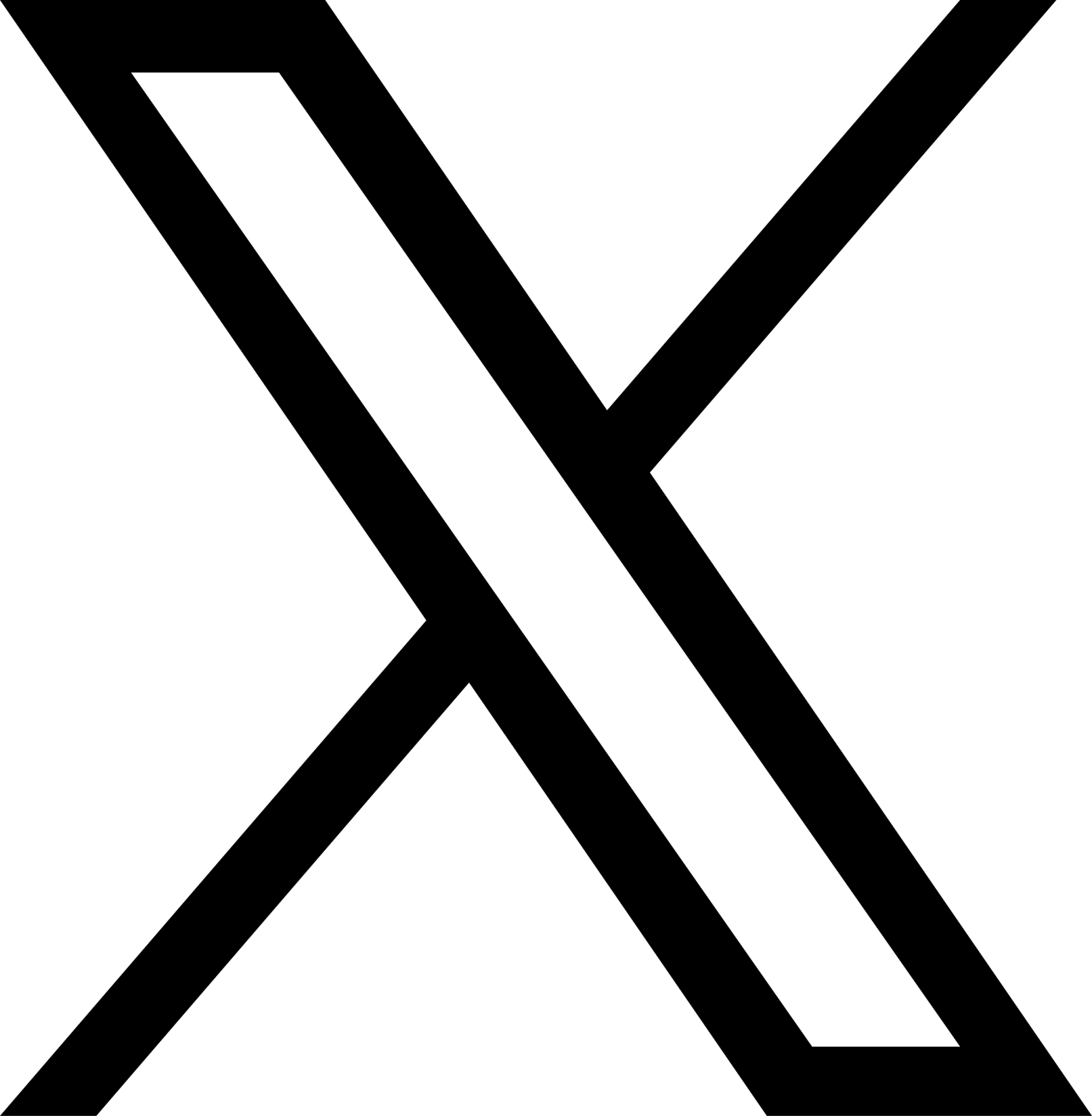
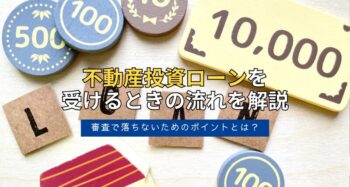
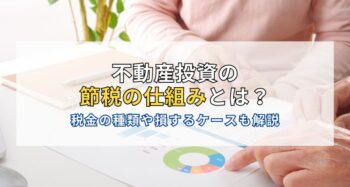

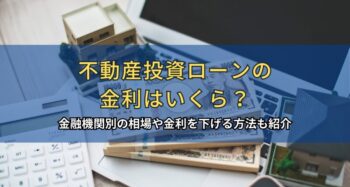
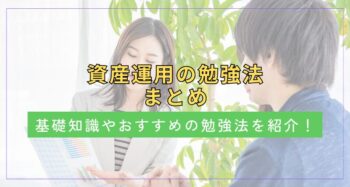



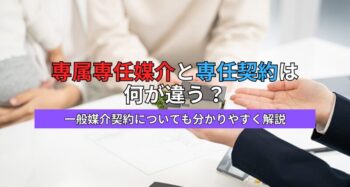
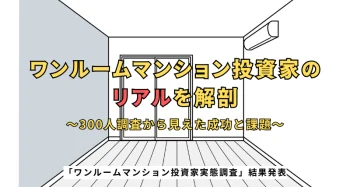
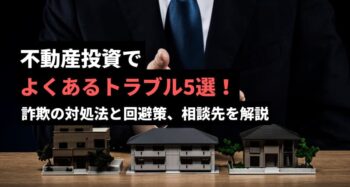
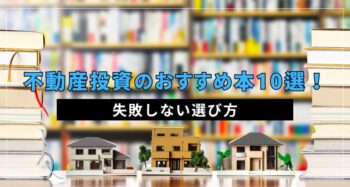
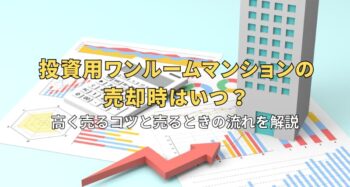

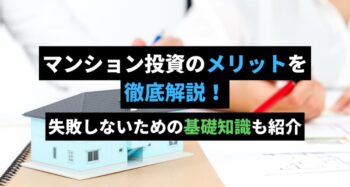

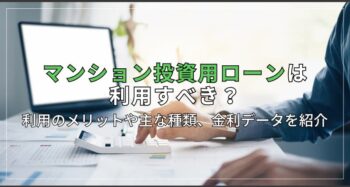

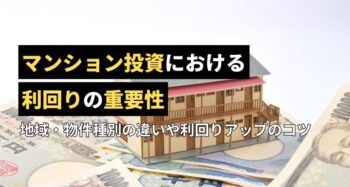

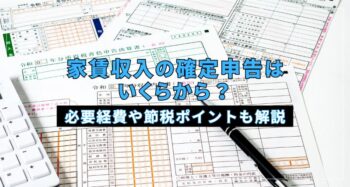
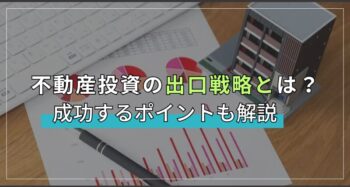
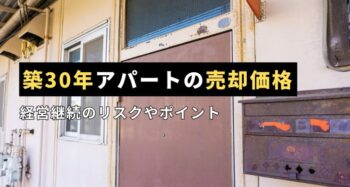
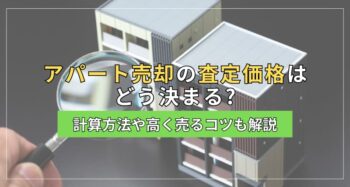

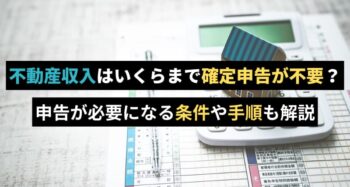
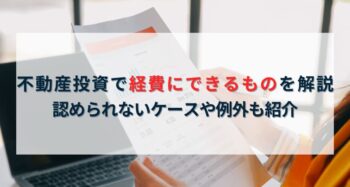
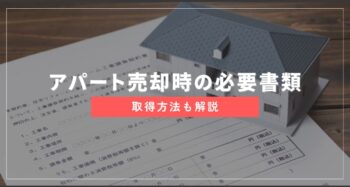


代表取締役伊藤幸弘
私がおすすめするのは、とにかく清潔感のある内装をきちんと維持することですね。特に水回りの綺麗さは重要です。スイッチやコンセントカバーも、黄ばんでいたり傷みがあったら新しいものに変えていくことをおすすめします。
水回りについては、新品に取り換えるよりも、コーティングという方法がおすすめですよ。車のコーティングと同じような感じで、まず徹底的に清掃して汚れを落として、その後にコーティング材を施すんです。そうすると、ピカピカの新品に近い輝きが戻りますし、2、3年は効果が持続するんです。コストパフォーマンスも良いですよ。
あとは建具の交換や木部の塗装も重要です。意外と見落としがちなんですが、木のドアや窓枠の日焼けや色落ちは物件の印象を大きく下げてしまいます。ペンキ職人さんに頼んで塗装すれば見違えるように綺麗になりますよ。
照明も大切なポイントです。暗い部屋には誰も住みたくないですからね。同じ部屋があったら、やっぱり明るくて清潔感のある方を選びますよね。
私が心がけているのは、お金をかけすぎずにちゃんと綺麗な状態を維持することです。フルリノベーションも効果はありますが、投資した費用を何年で回収できるかをしっかり考える必要があります。賃貸は結局、利回りが重要なので、その点も忘れないようにしています。
あと、初期費用を下げることも考えましょう。つまり敷金・礼金を抑えめにすることで、入居者にとって魅力的な物件に見えるようにします。それから、地域の不動産業者さんを直接回って、「私は○○のオーナーですが、この部屋が空いているので、お客さんがいたら紹介してください」というように営業活動をするのも効果的です。1週間後に電話で状況を確認するなど、フォローアップも忘れずにやります。これって意外と効果があるんですよ。不動産業者さんも「あ、このオーナーさん熱心だな」って思って、お客さんを紹介してくれやすくなります。
基本的には、綺麗な状態を維持して、目に触れる機会を増やすということが大切。家賃を下げるという選択肢は、本当に最後の手段として考えるべきです。なぜなら、一度下げてしまうと、今後の収支に大きく影響してきますし、売却時の価格にも響いてきますからね。