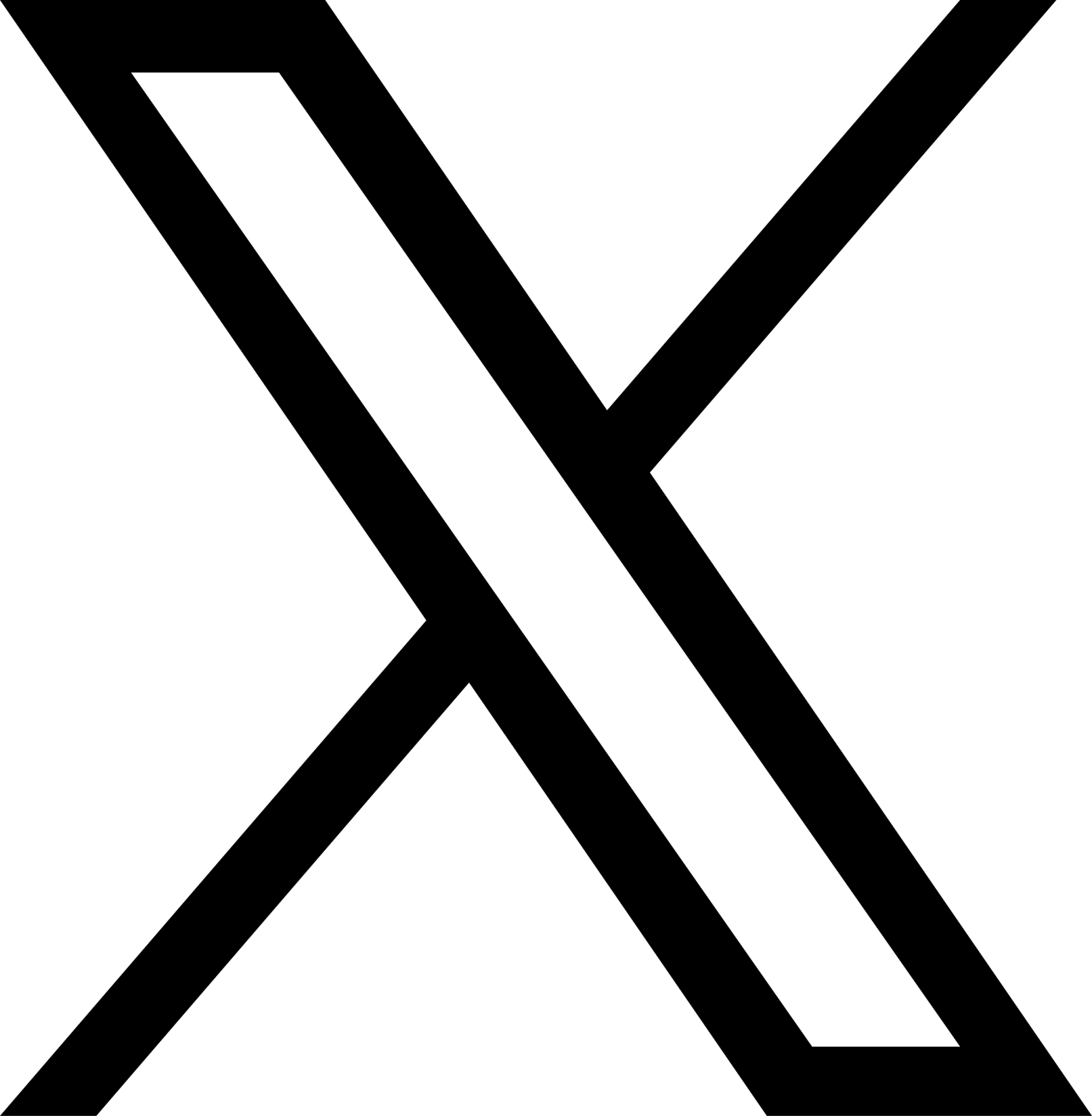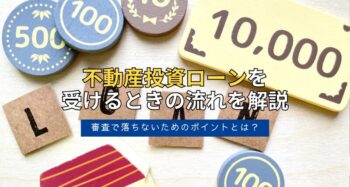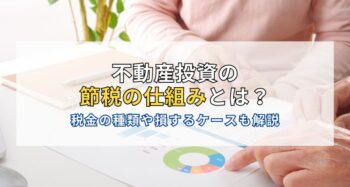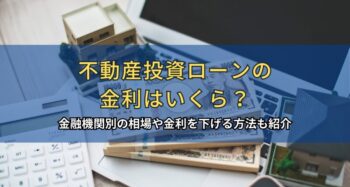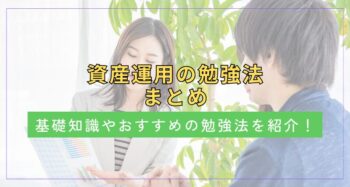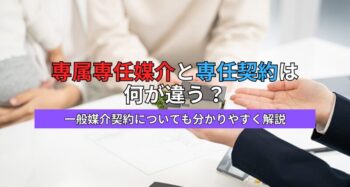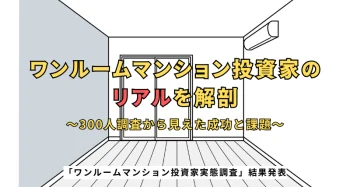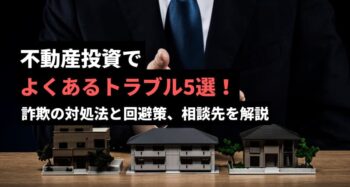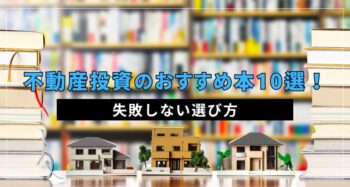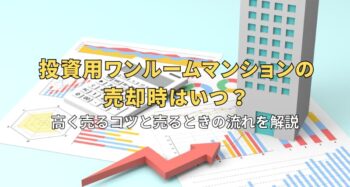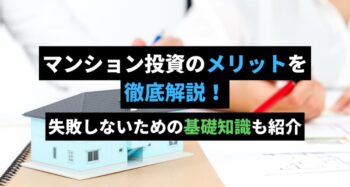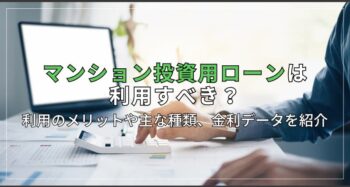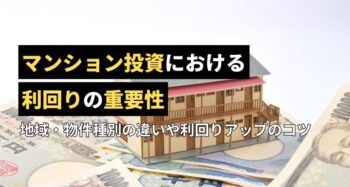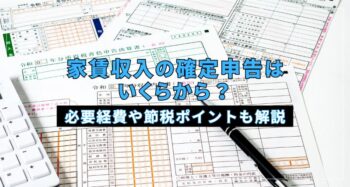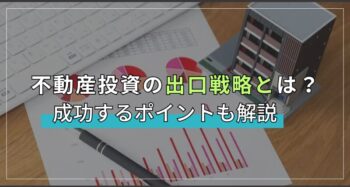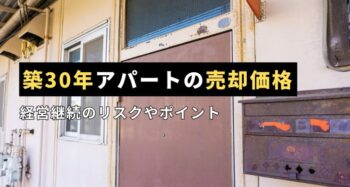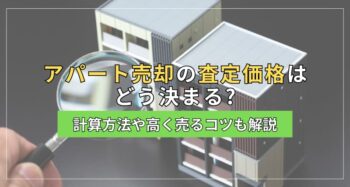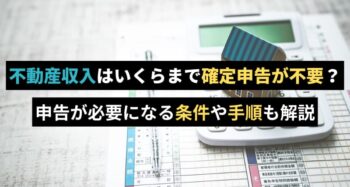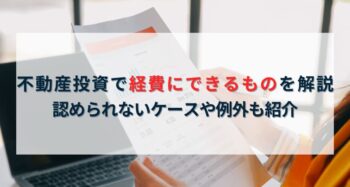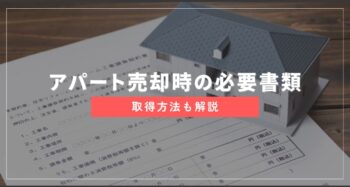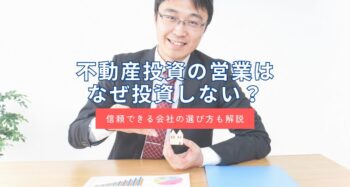
投資マンション基礎知識
不動産投資詐欺の手口8選!悪徳業者の見分け方と騙されないためのポイント

不動産投資は将来の資産形成に役立つ一方で、予期せぬトラブルに巻き込まれることがあります。
特に、一部の悪質な業者による詐欺被害が報告されており、事前に対策を知っておくことが大切です。
不動産投資における代表的な詐欺の手口8選を紹介し、被害を防ぐためのポイントを併せて解説します。
安全に投資を行うためにも、事前にしっかりと知識を身につけましょう。
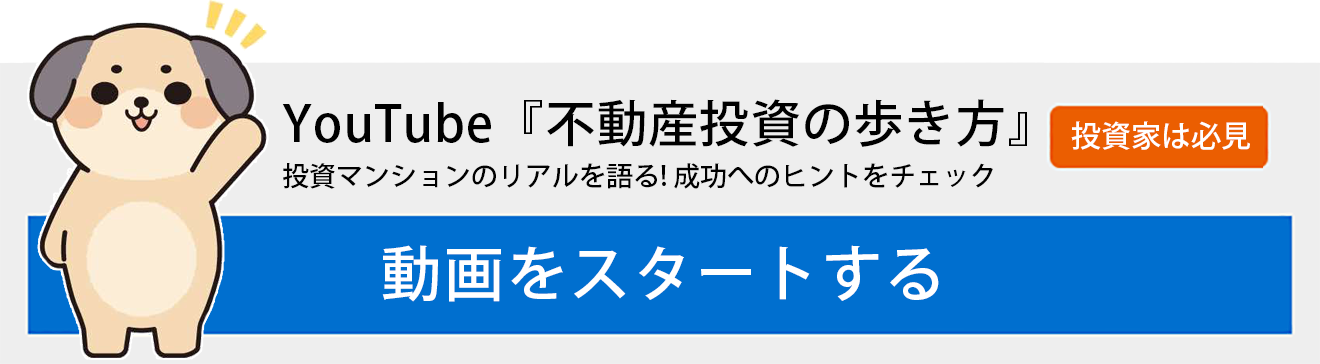
目次
不動産投資で注意すべき詐欺の手口
不動産投資における詐欺にはさまざまな手口があります。そのため、詐欺の手口を理解することで、被害を未然に防止できるかもしれません。
不動産投資で代表的な8つの詐欺について一つずつ紹介していきます。
二重譲渡詐欺
不動産投資の詐欺手口の1つ目は、「二重譲渡詐欺」です。
二重譲渡詐欺とは、売主Aさんが買主Bさんに売却済みの物件を、第三者のCさんにも売却する詐欺のことです。
不動産の所有権は契約だけでは確定せず、登記を先に済ませた人が法的に優先されます。
そのため、BさんがAさんと最初に売買契約を結んでいても、Cさんが先に登記を済ませてしまうと、不動産の正当な所有者はCさんとなってしまうのです。
二重譲渡詐欺の被害に遭うと、売買代金を支払ってもどちらか一方は物件を所有することができません。
不動産の購入は決して安い金額ではないため、被害に遭うと数千万円以上の損害を受けることになります。
そのため、以下の点に注意して、契約を進めることがポイントです。
- 事前に登記簿謄本を確認する
- 信頼できる不動産会社に依頼する
売買契約だけでは不動産の所有権は確定しない、ということを覚えておきましょう。
サブリース詐欺
不動産投資の詐欺手口の2つ目は、「サブリース詐欺」です。
サブリース詐欺の前に、まずはサブリース契約について簡単に説明します。
サブリース契約とは、サブリース会社がオーナーから賃貸物件を一括で借り上げるため、入居者の有無にかかわらず一定の賃料収入が見込める契約です。
サブリース詐欺とは、「10年間は家賃を保証します」「家賃はこの金額から下がりません」と説明したにもかかわらず、実際には数年間しか家賃保証をしない、途中で契約を打ち切られるなどの詐欺のことです。
2020年6月の「賃貸住宅管理業法(サブリース新法)」改正により、現在はサブリース契約に関する誇大広告や不当表示は禁止されました。
また、契約前に重要事項説明を行うことが義務化され、オーナーに契約のリスクを説明することが求められています。
しかしながら、法改正後にすべての業者が適切に対応しているとは限りません。納得できるまで内容を確認し、不安がある場合は契約前に専門家へ相談しましょう。
参考:国土交通省「賃貸住宅管理業法ポータルサイト」
リースバック詐欺
不動産投資の詐欺手口の3つ目は、「リースバック詐欺」です。
リースバックとは、自宅を不動産会社などに売却した後、家賃を支払って賃貸物件のように住み続ける契約のことです。
この契約を活用することで、物件の所有者は住む家を確保しながら、まとまった現金を得ることができます。
しかし、悪質な業者は不動産の売却金額を安く、逆に家賃価格を高く設定するリースバック契約を勧めてくることがあります。
その結果、家賃が払えなくなり自宅から退去を求められる事例が報告されています。リースバック詐欺を防ぐには、契約前に複数の業者から見積もりを取り、契約内容を十分に確認しましょう。
買取相場をきちんと把握することは、売却金額が安い不動産会社を避けることにつながります。
ワンルームマンション投資詐欺
不動産投資の詐欺手口の4つ目は、「ワンルームマンション投資詐欺」です。
ワンルームマンション投資詐欺とは、不動産購入の際に、高い利回りを提示して優良物件に見せかける詐欺のことです。
不動産投資では、投資から得られる利益を計算した、利回りが重要と言われています。しかし、利回りは2種類あります。
- 表面利回り:年間の家賃収入を購入費用で割った利回り
- 実質利回り:表面利回りから、維持管理にかかった費用を差し引いた実際の利回り
表面利回りだけを見て「優良物件だ」と思い込むと、実際は維持費や管理費を考慮した実質利回りが低く、損をする可能性が高くなります。
不動産会社が提示する利回りがどちらなのか正しく理解できると、詐欺の被害に遭いづらくなるでしょう。
原野商法
不動産投資の詐欺手口の5つ目は、「原野商法」です。
原野商法では、市場価値の向上が見込めない原野や山林などの土地を「今後値上がりする」と謳い、購入を促すのが特徴です。
1970年代に流行した際は、「土地を高く買い取ります」と甘い言葉で投資家を勧誘し、測量サービスに契約させるという二次被害トラブルも発生していました。
近年では、「以前に購入した原野を買い取る」と持ちかけ、一度売却させた後にさらに高額な別の原野を購入させる詐欺が目立っています。
原野商法の手口は多様化してきていることから、特に高齢者が被害に遭うケースが増加しているとのことです。
被害を防ぐためには、複数の専門家に相談したり不動産の市場価値を事前に調査したりと、慎重な対応を心がけてください。
参考:政府広報オンライン |「「原野商法」再燃!「土地を買い取ります」などの勧誘に要注意」
満室偽装詐欺
不動産投資の詐欺手口の6つ目は、「満室偽装詐欺」です。
満室偽装詐欺とは、空室が多い物件にサクラとして故意に入居者を増やし、一時的に入居率が高い人気物件を装う詐欺のことです。
満室偽装詐欺に遭うと、物件の売却後にサクラの入居者が一斉に退去し、空室だらけの物件になってしまいます。その結果、物件の購入者は想定していた賃料収入を得られないというわけです。
満室偽装詐欺の被害を未然に防ぐために、レントロールという賃貸物件の契約一覧を確認することがポイントです。
手付金詐欺
不動産投資の詐欺手口の7つ目は、「手付金詐欺」です。
手付金詐欺とは、物件購入のために入金した手付金を持ち逃げされて、物件を手に入れられない詐欺のことを指します。
この詐欺の特徴は、「人気物件だからキープしておかないと他の人が先に契約しますよ」などと言い、手付金の支払いを催促するケースが多いところです。
また、宅地建物取引業法の39条では、手付金は売買価格の20%以下でなければならない、と定められています。そのため、手付金が相場よりも高い場合は注意しましょう。
手付金詐欺を避けるポイントは、「手付金の支払いを急かしてくる不動産会社は避ける」ことです。
支払いを急かす不動産会社との取引は、安全に取引できるか慎重に確認する必要があります。
参考:e-Gov 法令検索 |「宅地建物取引業法」
海外投資詐欺
不動産投資の詐欺手口の8つ目は、「海外投資詐欺」です。
海外投資詐欺は、投資先の物件が海外にあるといい、実際に存在しない物件や価格を高く設定して販売する詐欺手法のことです。
不動産の購入者は、取引対象の不動産が海外にあると思い込んでいるため、十分な判断ができないまま契約してしまいます。
不動産を購入する際は、実際に現地調査をして確認するのが基本です。どんなに条件が良かったとしても、「現地調査できない物件には手を出さない」と決めておくのもよいでしょう。
個人情報の登録不要!ワンルームの価格がわかる
「TOCHU iBuyer」
不動産投資の詐欺を行う怪しい不動産会社の特徴
不動産投資に関する詐欺の手口は巧妙なので、被害に遭ってしまう投資家の方もいます。
しかし、詐欺を行う不動産会社には以下のような特徴があります。
- 突然自宅に押しかけてみたり街頭で声をかけたりする
- 不動産投資に関する説明が足りない
- 収入に合わない高額なローンを勧められる
- クーリングオフをさせないようにする
1つずつ解説していきます。
自宅に押しかけたり街頭で声をかけたりする
自宅に押しかけて契約をしようとする不動産会社には気を付けて下さい。
宅地建物取引業法の第37条の2により、クーリングオフ制度は原則として売主(宅地建物取引業者)の事務所や案内所以外の場所で、買主が契約や申込みを行った場合に限ります。
一方、買主が事務所や住宅展示場に自ら出向いて売買契約を締結した場合や、売主の事務所で契約を締結した場合はクーリングオフの適用外となります。
また、街頭で名刺交換を依頼された場合にも断った方が良いでしょう。交換すると不動産会社の営業リストに乗り、勧誘電話が頻繁にかかってくる可能性があるからです。
不動産投資を考えていない場合は、はっきりと断ることが大切です。
参考:e-Gov 法令検索 | 「宅地建物取引業法」
不動産投資に関する説明が足りない
不動産投資に関する説明が不足している不動産会社にも注意が必要です。
なぜなら、不動産知識が不足している購入者を狙って詐欺を仕掛けてくるからです。
具体的には、以下のようなケースが挙げられます。
- 賃貸経営に必要な費用の説明がない
- 築年数と入居率の関係性を伝えない
- 物件の瑕疵について説明をしない
物件を売るために、費用を考慮しない表面利回りのほうを提示する不動産会社には要注意です。
また、再建築不可の物件であったり、事件が起きた物件だったりすると、入居者が集まりづらいため想定通りの家賃収入が得られない可能性があります。
物件情報を正確に十分に説明してくれる不動産会社を選ぶようにしましょう。
収入に合わない高額なローンを勧められる
収入よりもはるかに高いローンを勧められた場合、詐欺を疑った方がいいかもしれません。
悪徳業者にとっては不動産が売れればそれでよく、購入者がローンを返済できるかどうかは関係ないからです。
実際、収入や資産が少ないにもかかわらず不動産の購入を勧められた事例があります。
- 家賃収入で返済できるから安心して下さい
- 不動産価格が上昇しているから、今購入するのがお得です
などと勧められて、20代の方が投資用マンション購入のため2,000万円以上のローンを組んでしまいました。
収入に見合わないローンを組むと返済が困難になるため、収入に見合ったローンを組むことが大切です。
クーリングオフをさせないようにする
クーリングオフをさせない不動産会社には注意が必要です。
クーリングオフとは、契約締結後8日以内であれば、消費者が無条件で契約を解除できる権利のことです。
しかし、不動産会社の事務所や案内所で契約を締結すると、クーリングオフが適用されません。
また、クーリングオフは購入者の権利ですが怪しい不動産業者の場合は
- こんなおいしい話は他にはありませんよ
- 違約金がかかるから解約すると損しますよ
などと理由をつけて、契約の解除を引き止められるケースもあるようです。クーリングオフは8日以内に対応する必要があるため、怪しいと感じたときは迷わず処理を進めましょう。
不動産投資で詐欺に遭わないための対処法
不動産投資は大きなお金が動くため、被害に遭うと損失も大きいといわれています。
そのため、以下のような詐欺に遭わない対策をとることが重要です。
- 不動産投資について知識を深める
- 疑問点や不安に思ったことは必ず質問する
- 契約書の内容を細かく確認する
1つずつ解説していきます。
不動産投資について知識を深める
不動産投資で詐欺に遭わないための対策の1つ目は、「不動産知識を身に着けること」です。
まずは、書籍を読んだりセミナーに参加したりして、不動産投資に関する知識を身に着けるとよいでしょう。
不動産投資について学ぶことで詐欺から身を守れるだけでなく、不動産投資の成功率を高められます。
現在は、インターネット上でも無料セミナーが数多く実施されているため、手軽に不動産投資の勉強を始められます。不動産投資を始めたいという人は、興味がある内容からでもいいので、少しずつ勉強を始めましょう。
疑問点や不安に思ったことは必ず質問する
不動産投資で詐欺に遭わないための対策の2つ目は、「疑問や不安に感じたことは必ず確認すること」です。
不動産投資では、物件の選定や契約の締結など、大きな判断が求められることがあります。その際、売却価格や契約内容で疑問に思うことが出てくることがあるかもしれません。
信頼できる不動産会社は、投資家の疑問に対して丁寧に説明し、納得できるまで回答してくれるものです。
逆に、質問に対して曖昧な回答をする、契約を急かすといった対応をする業者には注意が必要です。不動産投資のリスクを最小限に抑えるためにも、契約前に納得できるまで質問し、透明性のある取引を心がけましょう。
契約書の内容を細かく確認する
不動産投資で詐欺に遭わないための対策の3つ目は、「契約書の細部まで確認する」ことです。
契約書を詳細に確認することで、不利な条件に気づける場合があります。また、契約解除の条件や違約金について明確に記載されていない場合、必ず不動産会社に確認してください。
契約内容で分からないことがあれば、第三者の専門家に確認するのもよいでしょう。契約書の内容を細かく確認することは、不動産投資詐欺に遭わないためにも重要なポイントです。
投資マンションの価格を手軽に知るなら
「マンションPrice」
不動産投資で詐欺にあった場合の対応策
不動産投資詐欺に気を付けていても、被害に遭ってしまうケースもあります。
もし被害に遭ってしまった場合、以下の施設に相談しましょう。
- 免許行政庁
- 消費者生活センター
- 宅地建物取引業保証協会
- 弁護士
- 警察
詐欺被害に遭ってしまった場合、自分一人で解決するのは難しいでしょう。上記の機関に相談し、いち早く解決できるように取り組むのがおすすめです。
あなたのマンション・アパートの価格が分かる