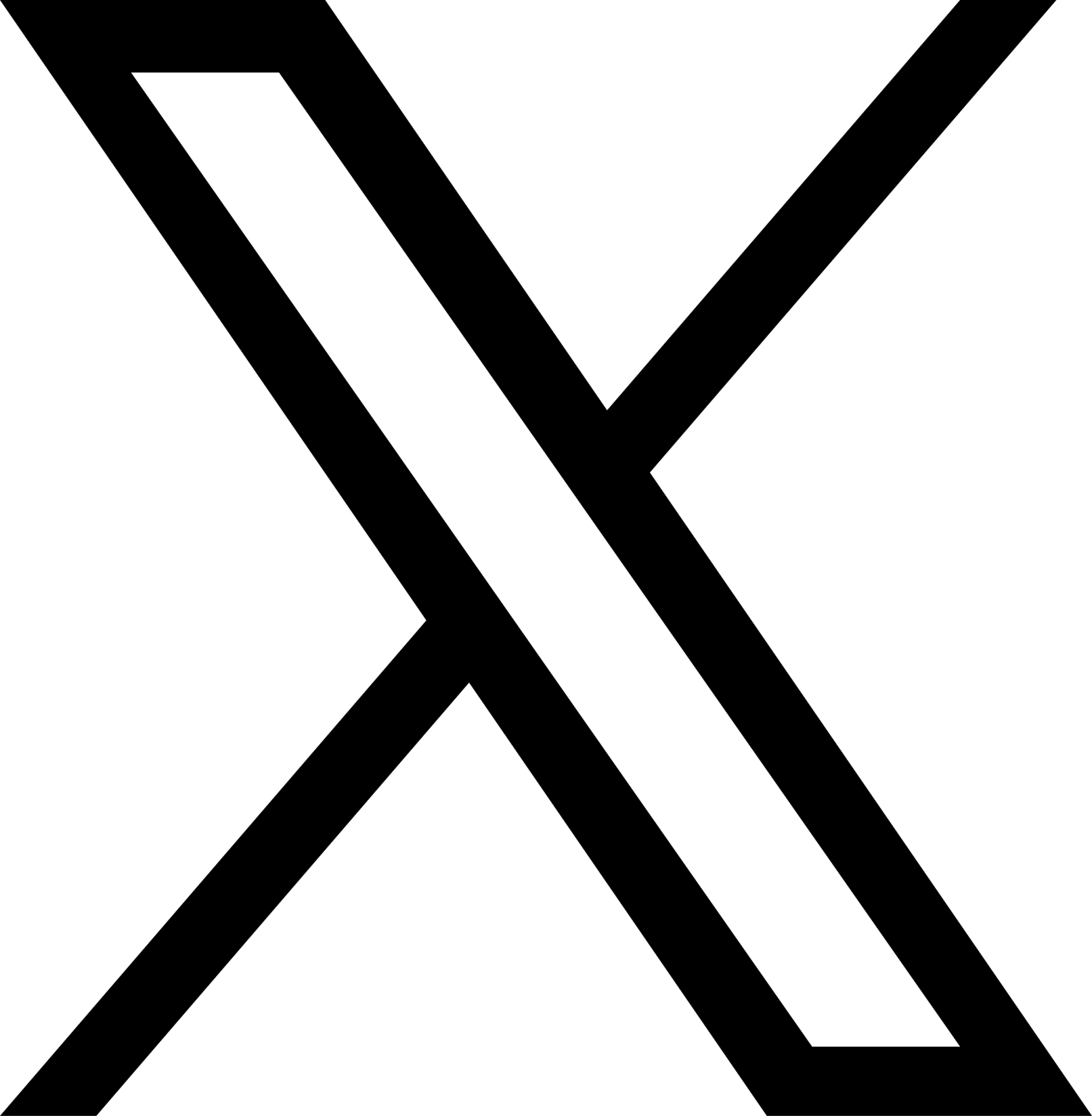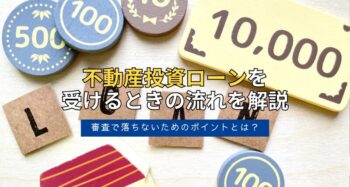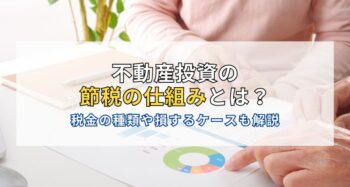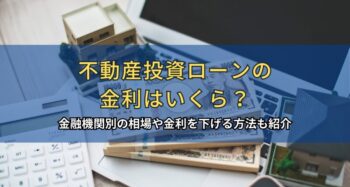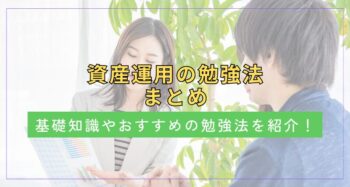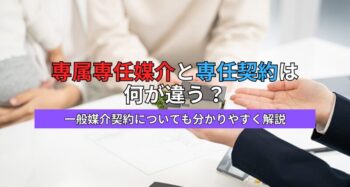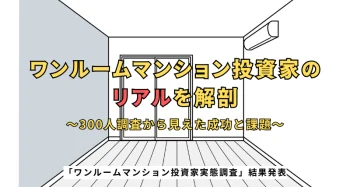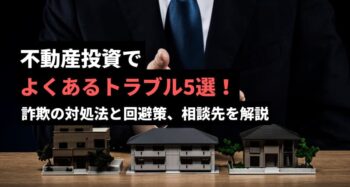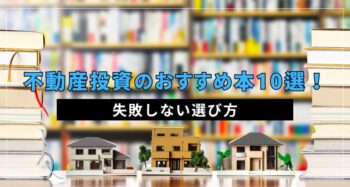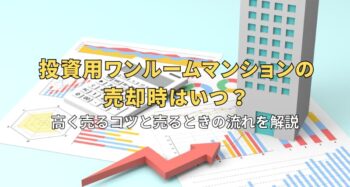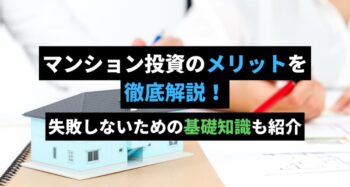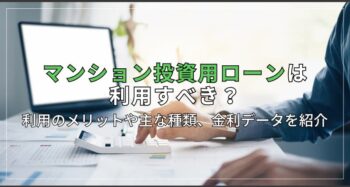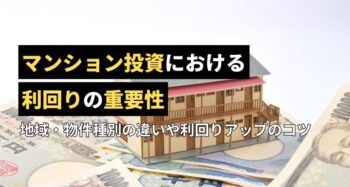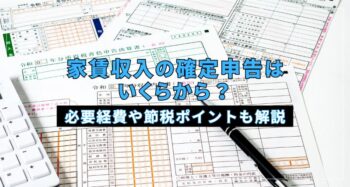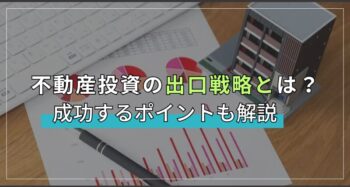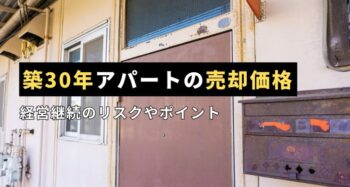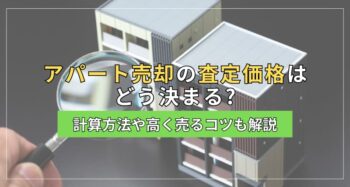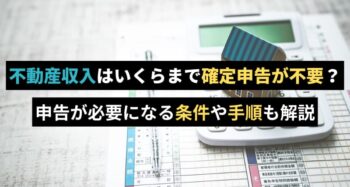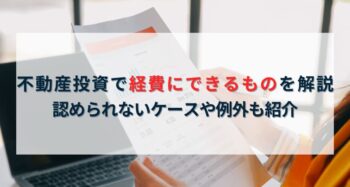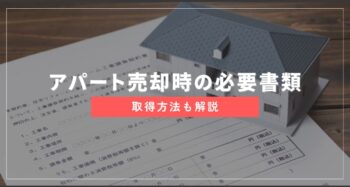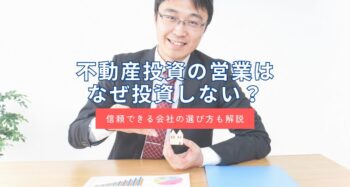
不動産投資
アパートを相続したほうがいい?節税対策や売却する際の判断基準も紹介

アパートを相続した際、売却すべきか所有し続けるべきかで悩む方は少なくありません。
賃貸経営を行うと家賃収入や節税効果などのメリットがある一方、空室リスクや管理費用などのデメリットも存在します。
アパートを相続した際の相続か売却するかの判断基準、具体的な節税方法について詳しく解説します。
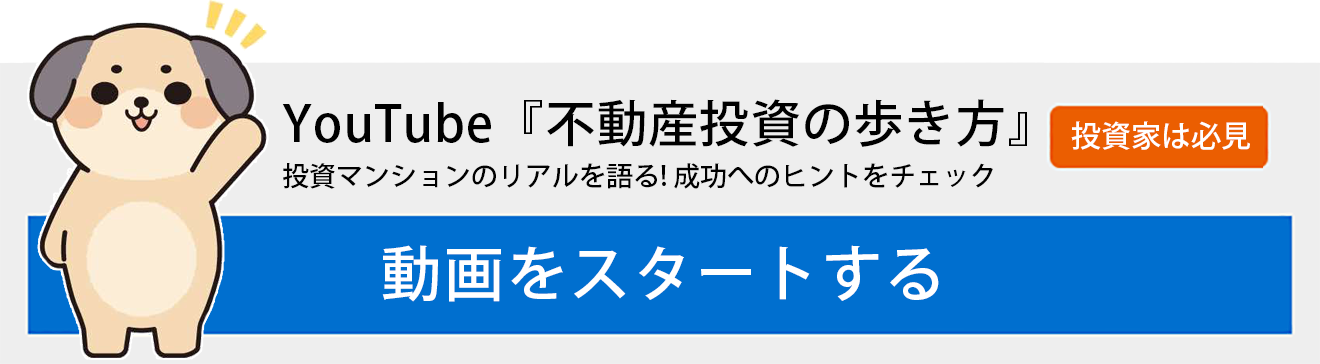
目次
アパートを相続した場合のメリット
アパートを相続することには、さまざまなメリットがあります。
相続と聞くと、相続税の負担や管理の手間を心配する方も多いですが、適切に運用すれば資産として大きな価値を持ち、将来的な利益につながる可能性もあるでしょう。
アパートを相続することによる具体的なメリットについて詳しく見ていきます。
家賃収入が毎月得られる
アパートを相続する大きなメリットの一つは、毎月安定した家賃収入が得られる点です。
入居者がいる限りは定期的に収益が入るため、相続した人の生活を支えることもあります。特に、立地が良く空室率の低いアパートであれば、安定した収入が見込めるでしょう。
相続後すぐにアパートの売却を検討する人もいますが、売却せずに運営を続けることで、長期的に収益を得る選択肢もあります。
さらに、家賃収入は年金や給与以外の収入源に分類されるため、老後の生活資金として活用することも可能です。
金融機関からの融資を受ける際に、家賃収入があることで信用力が高まり、追加の資産運用や投資に活用できる可能性もあります。
ただし、アパート経営で安定した収入を得るには、適切な管理が必要となり、入居者の募集や建物の維持費などを考慮する必要があります。
アパートを相続することで節税できる
アパートを相続することは、相続税の負担を軽減する大きなメリットがあります。
相続税は、相続した財産の評価額に基づいて課税されますが、不動産は現金とは異なり、一定の評価基準により税額が抑えられるケースが多いです。
では、現金5,000万円を相続した場合と、5,000万円で購入したアパートを相続した場合の相続税の違いを比較し、具体的な節税効果を見ていきます。
参考:国税庁|No.4602 土地家屋の評価
現金で5,000万円を相続した場合
現金で5,000万円を相続した場合、相続税の負担が大きくなる可能性があります。
相続税は、基礎控除額を超えた部分に課税されます。基礎控除額は「3,000万円 + 600万円×法定相続人の数」となっており、例えば法定相続人が1人の場合、基礎控除額は3,600万円です。
そのため、5,000万円の現金を相続した場合、課税対象となる金額は1,400万円となります。1,400万円という課税対象額に対して相続税率が適用されるため、実際に支払う相続税は約160万円です。
現金をそのまま相続すると、資産評価額がそのまま相続税の課税対象となるため、相続税の負担が比較的高くなる傾向があります。
また、現金の場合は節税対策が難しく、減税する手段も限られるため、他の資産を活用した相続対策を検討するのも一つの方法です。
参考:国税庁|No.4152 相続税の計算
5,000万円で購入したアパートを相続した場合
アパートなどの不動産は、現金と違って相続税を計算するときの評価額が実際に購入した価格よりも低くなるのが一般的です。
アパートの相続税評価額は建物と土地で異なります。
- 建物:固定資産税評価額(建築時価格の約50~70%)
- 土地:路線価(市場価格の約70~80%)
例えば、5,000万円で購入したアパートの建物評価額は3,500万円(70%の場合)です。
「貸家評価の特例」が適用された場合はさらに評価が30%減少し、建物評価額は2,450万円になります。
一方、土地の価値が2,500万円とすると、借地権割合が50%のとき評価は1,250万円になります。この結果、5,000万円のアパート全体(建物+土地)の評価額は3,700万円です。
そこから基礎控除額の3,600万円を差し引くと、課税対象額は100万円となり、実際に支払う相続税は約10万円まで軽減できます。
現金5,000万円をそのまま相続した場合の相続税は160万円ですので、大幅な節税になるといえるでしょう。
参考:国税庁|財産を相続したとき
将来的に自分や家族が住むことができる
アパート相続のメリットとして、将来的に自分や家族が住める点が挙げられます。
相続したアパートを賃貸として運用するだけでなく、ライフステージの変化に応じて自身が住む場所として活用することも可能です。
例えば、子どもが独立して広い家が不要になった場合や、老後に利便性の高い立地へ移り住みたいと考えた際に、相続したアパートの一室を自宅として利用することで、新たに住宅を購入するコストを抑えられます。
また、親族が住む場所として活用できるため、賃貸経営が難しくなった場合の選択肢としても有効です。
ただし、アパートの築年数や設備の老朽化によっては、住む前にリフォームや修繕が必要になることも考えられます。相続時点で物件の状態を確認し、将来的に自分や家族が住む可能性があるかどうかを検討しましょう。
個人情報の登録不要!ワンルームの価格がわかる
「TOCHU iBuyer」
アパートを相続したことで発生するデメリット
アパートの相続にはさまざまなデメリットもあります。
例えば、相続したアパートをそのまま所有し続ける場合、管理や修繕の負担、相続人同士のトラブルなど、予想外の問題が発生するかもしれません。
また、空室リスクや修繕費の負担が大きくなると、想定していた収益を確保できないケースもあります。
アパートを相続したことで発生する主なデメリットについて詳しく解説します。
共有名義は相続トラブルのリスクが高い
アパートを相続する際に、共有名義にすると相続人同士でトラブルが発生する可能性があります。
相続人が複数いるときは、アパートを単独で相続するのではなく兄弟や親族と共有名義で所有するため、意思決定が難しくなることが大半です。
例えば、自分がアパートを売却したい、または建物の老朽化に伴い解体したいと考えた場合、共有名義人全員の同意が必要です。
1人でも反対する方がいれば売却や解体ができず、結果として管理が滞り、資産価値の低下につながるリスクもあります。
また、家賃収入の分配や修繕費用の負担割合についても意見が分かれ、トラブルに発展することも考えられます。
そのため、アパートを共有名義で相続する場合は、事前に相続人同士で話し合いを行い、管理方法や将来的な売却について取り決めをしておきましょう。
共有名義によるトラブルを避けたい場合は遺産分割協議を行い、単独名義にする方法も検討してください。
家賃収入がマイナスになることがある
アパートを相続すると家賃収入が得られる一方で、収支がマイナスになるリスクも考慮しなければなりません。
アパートの築年数が古くなると入居者が集まりにくくなるだけでなく、老朽化した設備の修繕やリフォームに多額の費用がかかります。
また、管理会社に委託している場合は管理費や手数料が発生するため、収支バランスを計算しないと赤字経営になってしまうでしょう。
さらに、アパートの立地や周辺環境の変化によっては、家賃相場が下落するケースも考えられます。例えば、近隣に新しいマンションや競合物件が増えると、賃料を下げなければ入居者を確保できず、結果として収入が減少することもあるでしょう。
建物の修繕や入居者の対応を行う必要がある
アパートを相続すると、建物の修繕や入居者の対応といった管理業務が発生することもデメリットです。
相続したアパートの築年数が古いと設備の劣化が進んでいることが多く、大規模なリフォームや耐震補強工事が必要になる場合もあります。
修繕にはまとまった費用がかかるため、計画的な資金管理が求められるでしょう。
また、家賃の滞納リスクも無視できません。入居者が家賃を支払わない場合、法的手続きを踏む必要があります。
そのほか、入居者からのクレームやトラブルへの対応、退去時の精算手続きなど、すべて自分で対応すると時間と労力がかかります。
管理会社に委託すれば負担を軽減できますが、その分管理費が発生するため、家賃収入とのバランスを考えることが大切です。
アパートを相続か売却するかの判断基準
アパートを相続するか売却するかを判断する際は、収益性や管理負担など総合的な観点から考えましょう。
アパートを相続したほうが良いケースと、売却したほうが良いケースについて詳しく解説します。
アパートを相続したほうが良いケース
相続したアパートの収益性が高く、管理や維持が負担にならないなら資産として活用しましょう。
アパートの立地が良く入居率も安定している場合は、長期的に見ても資産価値が維持される可能性が高いからです。
アパートを相続したほうがよいケースについて、具体的な条件をもとに解説します。
空室率が低いまたは満室の状態を保っている
アパートを相続したほうが良いケースの一つとして、空室率が低く、満室の状態を維持できている場合が挙げられます。
安定した家賃収入が見込める、資産としての価値を維持しやすい状況ということです。また、満室状態を維持しているアパートは、将来売却するときにも有利に働きます。
投資用不動産としての価値が高いため、空室の多い物件に比べて買い手が付きやすく、高値で売却できる可能性があるためです。
さらに、金融機関からの融資を受ける際にもプラスに働き、相続したアパートを担保にして新たな資産運用を行うことも検討できるでしょう。
ただし、現在の空室率が低いからといって将来も安泰とは限りません。長期的に見て競争力のある物件なのか、修繕費の必要は高額にならないかなどを考慮したうえで、相続するかどうかを判断しましょう。
アパートが好立地に建っている
アパートが好立地に建っている場合は、相続を検討する価値が十分にあります。
入居者の需要が高く、安定した家賃収入を確保しやすいため、資産としての価値が長期的に維持される可能性が高いからです。
特に、最寄り駅からの距離が近く、商業施設や学校、病院などの生活インフラが充実している、またはオフィス街の近くにある物件は、賃貸市場での競争力を保ちやすいでしょう。
さらに、立地が良いアパートは売却を考えた際にも有利に働きます。投資家や不動産会社の需要が高いため、買い手が見つかりやすく、相場よりも高値で売却できる傾向にあるからです。
将来的に都市開発や再開発の計画があるエリアでは、地価の上昇が期待できるため、相続後の資産価値がさらに高まるかもしれません。
ただし、いくら好立地でも建物自体が老朽化している場合や、修繕費用が高額になる場合は慎重な判断が必要です。
将来的に高い収益が見込める場合は相続を検討し、不動産の維持が難しいと判断したときは、売却を視野に入れましょう。
国や自治体の特例制度が利用できる
アパートを相続する際に、国や自治体の特例制度を利用できる場合は、相続を有利に進められます。特例制度を活用することで、相続税や譲渡所得税の負担を軽減でき、アパートを維持しやすくなるからです。
例えば、小規模宅地等の特例は、相続した土地の評価額を最大80%減額できる制度です。
アパートの敷地を相続し、相続税の申告期限まで賃貸経営を継続する場合、「貸付事業用宅地」として200㎡まで50%の評価減が適用されます。
ただし、相続後にアパートをすぐに売却してしまうと、適用対象外になるため注意が必要です。
また、「3,000万円特別控除」は、相続したアパートを売却する際に利用できる特例です。譲渡所得から最大3,000万円まで控除され、売却時の税負担を大きく減らせます。
例えば、相続したアパートを売却し、売却益が3,000万円以内であれば、譲渡所得税がかからない場合もあります。相続開始日(被相続人の死亡日)から3年を経過する年の12月31日までに売却する必要があるため、適用期限を必ず確認しましょう。
さらに、一部の自治体では老朽化したアパートの建て替え支援や、耐震改修の補助金制度を提供していることがあります。特例制度を活用すれば、アパートを相続後により管理しやすくなるでしょう。
参考:国税庁|No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
参考:国税庁|No.3302 マイホームを売ったときの特例
アパートを売却したほうが良いケース
相続したアパートを資産として活用できるかどうかは、物件の状態や経済的な負担、維持管理の難しさによって異なります。
例えば、相続税の支払いが困難であったり、ローン残債の返済が難しかったりする場合は、売却して現金化することで経済的な負担を軽減することが可能です。
アパートを売却したほうが良い具体的なケースについて詳しく見ていきましょう。
相続税の支払いが難しい
アパートを相続した際、相続税の支払いが難しい方は売却を検討するとよいでしょう。
相続税は相続した資産の評価額に基づいて課税されるため、資産価値の高いアパートを相続すると、その分相続税の負担も大きくなります。
特に、現金や金融資産が少なく、相続税の納税資金を確保するのが困難な場合、資産を維持し続けることが考えられます。
相続税の支払い期限は、被相続人が亡くなったことを知った翌日から10カ月以内です。短期間でまとまった資金を用意できない場合、相続税の納付が遅れると延滞税が発生し、さらに課税額が増えることになります。
また、相続税を支払うために他の資産を売却したり、借入をして対応したりすることもできますが、将来的に経済的な負担となる可能性も十分に考慮しましょう。
参考:国税庁|No.4205 相続税の申告と納税
ローンの残債が多く返済まで時間がかかる
アパートを相続した際に、ローンの残債が多く返済まで時間がかかる場合は、売却を検討するのが賢明でしょう。
亡くなった被相続人がアパートの購入や建築の際に借入をしており、そのローンがまだ残っている場合、相続人はその債務も引き継ぐことになります。
ローンの残高が多く、家賃収入だけでは十分に返済できない場合、毎月の返済額を補填するために自己資金を持ち出すことになるかもしれません。
アパートの市場価値がローンの残債を上回っている場合は、売却によってローンを清算し、さらに手元に資金を残すことができます。
反対に、市場価値がローン残高を下回る「オーバーローン」の状態になっている場合は、売却のタイミングを見極めましょう。
ローンなどの負債は相続放棄をすることで引き継がない選択も可能です。相続放棄をする場合は、相続開始から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
また、ローンの支払いが厳しい場合は、金融機関に相談して返済計画を変更したり、特定の条件を満たせば任意売却をしたりするのも一つの方法です。
空室率が高く入居者もいない
アパートを相続した際に、空室率が高く入居者もほとんどいない場合も売却を検討するとよいでしょう。
長期間にわたって空室が続くと家賃収入が得られないだけでなく、固定資産税や管理費、修繕費などの維持コストだけがかかり、赤字経営となるリスクが高まります。
空室率が高い主な原因として、立地の問題や家賃設定のミスマッチ、周辺の競争環境の変化などが考えられます。
例えば、地方にあるアパートの場合、人口減少の影響で賃貸需要が減少し、空室が埋まらないケースも多いようです。
売却を検討することで早めに資産を現金化し、他の投資や資産運用に活用できます。売却する際は不動産市場の動向を確認し、できるだけ高値で売れるタイミングを見極めるようにすることが大切です。
アパートの売却を不動産会社に依頼した際、自身でも相場価格を把握しておくと損なく売却を進められるでしょう。
アパートの老朽化が進んでいる
アパートの老朽化が進んでいる場合も、売却を検討したほうがよいケースです。
特に、築30年以上のアパートは新築やリノベーション済みの物件と比べて競争力が低く、家賃を下げても入居者が集まらないことがあるでしょう。
そして、築年数が古いアパートは維持管理のための修繕費がかさむ問題もあります。耐震基準を満たしていないアパートの場合は、耐震補強工事が必要になるため、その費用負担が大きくなるでしょう。
不動産は築年数が進むほど市場価値が下がり、買い手がつかなくなることがあるため、資産価値が低下する前に売却するほうが賢明な判断といえます。
アパートの老朽化が進んでいる場合は、維持管理にかかるコストと収益のバランスを見極めた上で、売却の選択肢を視野に入れてみてください。
あなたのマンション・アパートの価格が分かる