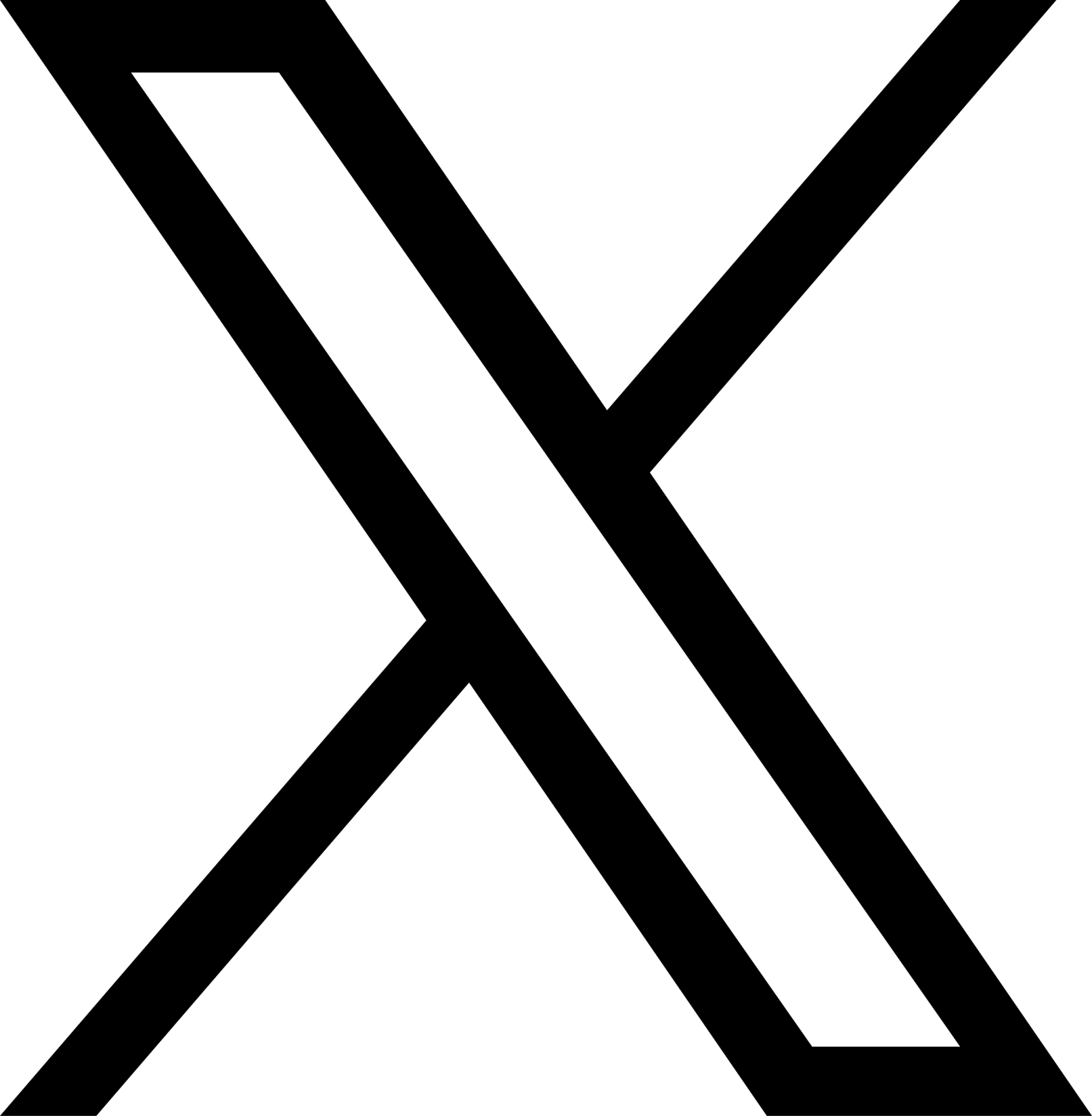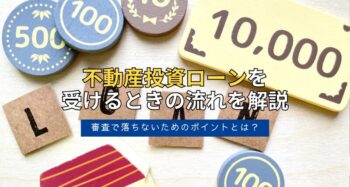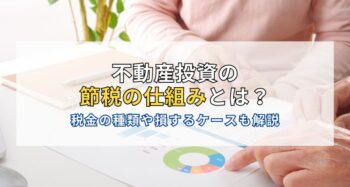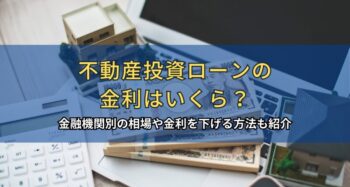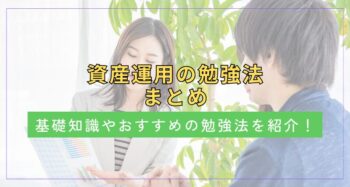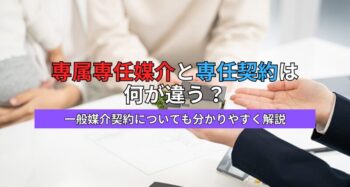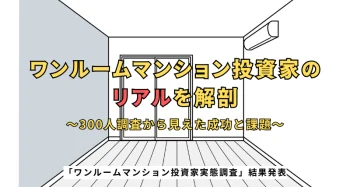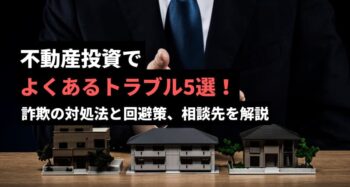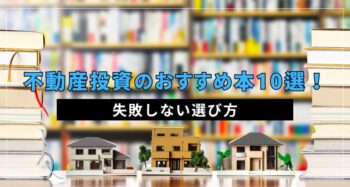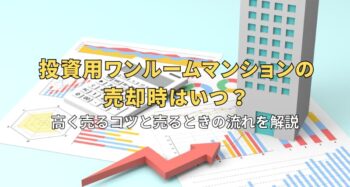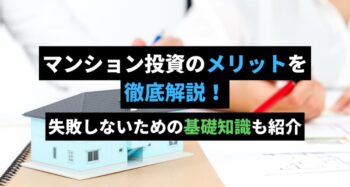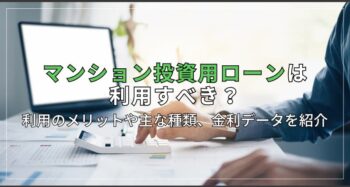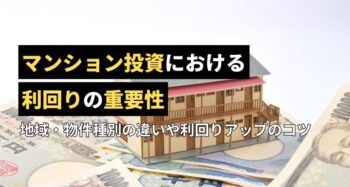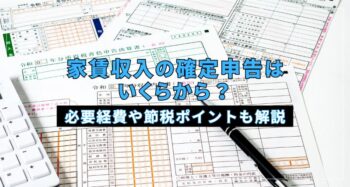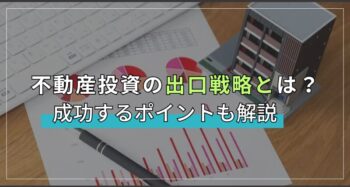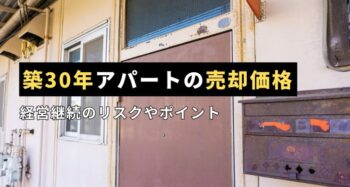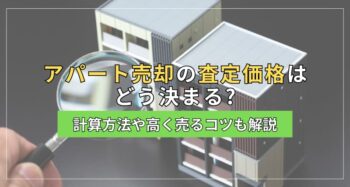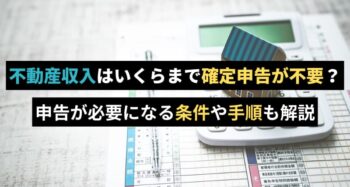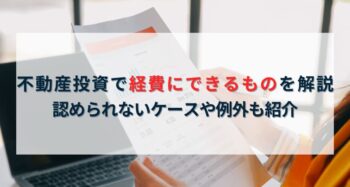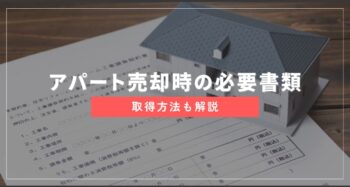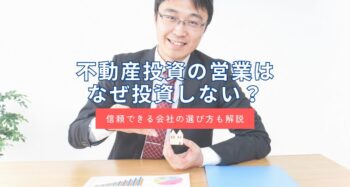
不動産投資
不動産投資の営業が投資しないのはなぜ?安全な会社の選び方も解説
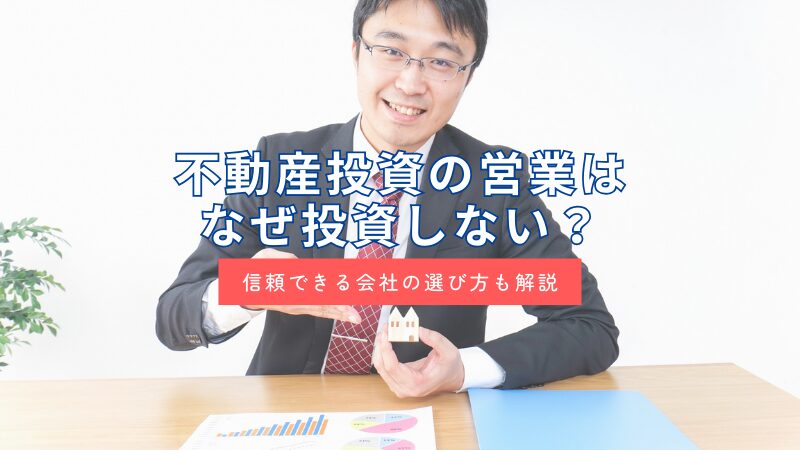
不動産投資の営業担当者は、さまざまな理由により自ら投資を行わないことがあります。
営業担当者が投資を避ける背景には、会社の規則や初期費用の負担、融資審査の難しさなどが挙げられるでしょう。
不動産の営業が投資しない理由のほか、美味しい話に騙されないためのポイントや信頼できる会社の見極め方について詳しく解説します。
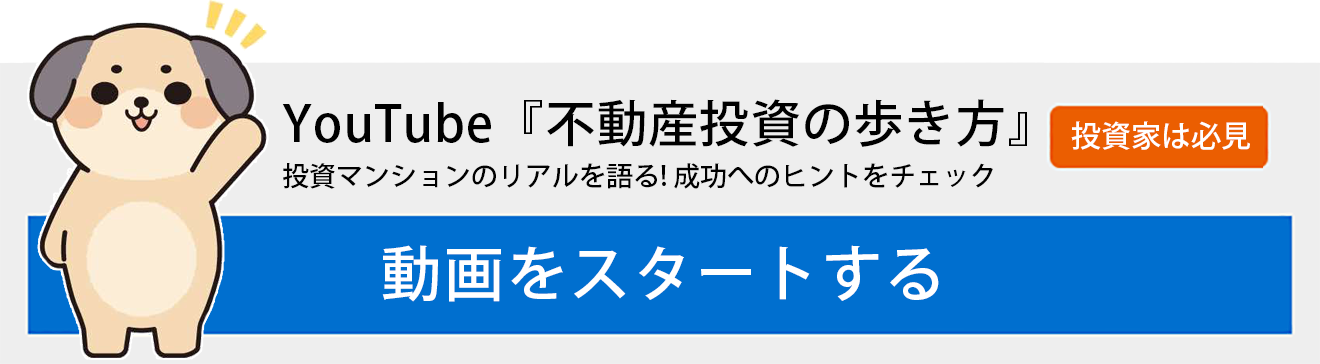
目次
不動産投資の営業が自分で投資しない理由
営業が不動産投資しない理由として、物件購入には高額な初期費用が必要であり、会社の給与体系によっては十分な資金を確保するのが難しいことが挙げられます。
また、勤務している会社の規定により、自社で取り扱う物件を購入できないルールが設けられている場合もあります。
不動産の営業担当者が投資しない理由について詳しく解説します。
初期費用が用意できない
不動産投資を始めるには、物件の購入費用のほかに、諸費用として手付金や仲介手数料、登記費用、ローンの頭金などが必要です。
初期費用は物件価格の10%〜20%程度はかかるのが一般的ですので、例えば3,000万円の物件を購入する場合、300万円から600万円ほどの自己資金が求められます。
不動産営業は歩合給の割合が高い職業であり、実績を積み高収入を得ている営業がいる一方で、経験が浅く成績も安定しないと年収が上がりにくいケースがあります。
特に若手の営業は、まとまった貯蓄を持っていないことも多く、高額な初期費用をすぐに用意するのが難しいようです。安定した収入がないとローンの審査に通りにくいこともあり、不動産営業が自ら投資を行わない理由の一つといえるでしょう。
自社物件を購入できないルールがある
不動産会社によっては、営業担当者が自社で取り扱っている物件の購入を禁止している場合があります。
自社物件を購入できないルールがある理由として、優良物件を営業担当者が優先的に購入してしまうと、顧客にとって不利益になる可能性があるからです。
また、社員が自社物件を購入することで、営業成績を意図的に操作できるため、公正な取引を維持するために制限が設けられることもあります。
公平性や利益相反を避けるため、自社が売主となる新築マンションや投資用物件を扱う企業では、営業自身の購入を制限しているケースは少なくありません。
さらに、不動産会社によっては、自社の社員が購入することでトラブルが生じるリスクを懸念し、一定期間の勤務が終了するまでは自社物件の購入を認めないなどの規定を設けている場合もあります。
投資をする目的が顧客と異なっている
不動産投資をする理由は人それぞれのため、不動産会社の営業と投資目的の顧客では目的が異なっていることがあるようです。
例えば、高所得者の顧客は節税対策を目的に一棟のマンションやアパートを購入し、不動産所得を活用して所得税や相続税の負担を軽減しています。
一方で、不動産会社の営業が投資を検討する場合、主な目的は資産運用です。不動産営業の多くは限られた自己資金の中で投資を行うため、一棟ではなく分譲マンションの一室を購入し、家賃収入を得ながらローンを返済していく方法を選ぶのが一般的です。
このように、営業と顧客では投資の目的が異なるため、不動産営業が積極的に自分で投資をしないケースもあるのです。
不動産会社の営業は銀行の融資を受けにくい
不動産会社の営業は、銀行の融資を受けにくい傾向があります。これは、営業職の給与体系や金融機関の審査基準が影響しています。
不動産営業は営業成績によって収入が大きく変動することがあるため、銀行側の中には返済能力を不安定と判断することもあり、融資の審査で不利になることが考えられます。
特に、入社して間もない場合や実績が少なく年収が低い営業の方は、融資を受けるのが難しくなることがあるのです。
また、不動産業界は景気の影響を受けやすく、銀行は業界全体をリスクの高い分野として見ていることがあります。個人で投資を行う場合、勤務先の経営状況や業界特有のリスクも審査の対象となるため、他の職業に比べて厳しい条件が課されることがあるようです。
さらに、不動産会社の営業が融資を申し込む際、銀行側が「自己使用ではなく投資目的である」と判断すると、住宅ローンではなくより金利が高く審査も厳しい投資用ローンが適用されるケースがあります。
その場合、借入条件がさらに厳しくなり、営業が自ら投資を行うハードルは一層高くなるのです。
投資よりもキャリアアップに力を入れている
不動産投資は家賃収入を得られる資産運用の方法の一つですが、物件の管理や入居者対応、修繕費用の計画など、手間や時間がかかるというリスクもあります。
そのため、不動産会社の営業の中には、投資を行うよりも自らのキャリアアップに力を入れたいと考える人もいます。特に、営業職は成果がダイレクトに給料へ反映されるため、実績を積み重ねることで昇進や給与アップを狙えます。
不動産会社によっては、営業成績が良ければ短期間で役職に就けたり、独立してさらに高い収入を得るチャンスもあったりするので、仕事に集中する方が効率的だと考える人も少なくありません。
また、不動産投資ではローンの審査を行うことが多く、一定の資金力や社会的な信用が求められます。
そのため、まずはスキルを磨き、経験を積んで収入を安定させてから不動産を購入しようと考えている方は、すぐに投資を始めることはないでしょう。
個人情報の登録不要!ワンルームの価格がわかる
「TOCHU iBuyer」
不動産投資の営業に騙されないためのポイント
不動産投資では悪徳業者による詐欺行為も報告されているため、営業担当者の態度や契約内容を冷静に見極めることが重要です。
例えば、高圧的な営業をする担当者は避けるべきですし、クーリングオフが可能かどうかを事前に確認しておきましょう。
不動産投資で詐欺やトラブルに巻き込まれないためのポイントを解説します。
高圧的な態度で接する営業は避ける
不動産投資は大きな金額が動くため慎重に判断すべきですが、なかには強引な営業手法を用いて契約を迫る営業担当者もいます。
初めは親しみやすい雰囲気だったのに、少しでも購入を迷う素振りを見せると急に態度を変え、「今決めないと損をする」などとプレッシャーをかけてくる営業もいます。
高圧的な態度を取る営業は、顧客の利益よりも自分の成績を優先している可能性が高いため、慎重に対応してください。
また、何度も断っているにもかかわらず執拗に連絡をしてくる営業も避けたほうが良いでしょう。しつこい勧誘は消費者契約法で禁止されており、悪質な場合は消費生活センターや国民生活センターに相談できます。
不動産投資は冷静な判断が求められる投資です。営業の態度が強引だったり、十分な検討時間を与えてくれなかったりする場合は、その会社や担当者とは距離を置くことが賢明です。
クーリングオフできるか確認する
不動産投資を検討する際は、契約後にクーリングオフが可能かどうかを必ず確認しましょう。
クーリングオフとは、一定の条件下で契約を無条件で解除できる制度で、訪問販売などの強引な営業手法から消費者を守るために設けられています。
不動産の取引では、宅地建物取引業者から事務所外で契約を持ちかけられた場合、8日以内であればクーリングオフにより契約を解除することが可能です。
ただし、契約場所が不動産会社の事務所やモデルルームであった場合、原則としてクーリングオフの適用外となるため注意が必要です。事業者がクーリングオフについて契約書面で告知しなかった場合は、契約から8日を過ぎてもクーリングオフを行えるケースがあります。
不動産投資では高額な契約が伴うため、万が一、冷静な判断ができないまま契約をしてしまった場合に備え、契約前にクーリングオフの適用条件を確認しておきましょう。
現地確認ができる物件を選ぶ
不動産投資を検討する際は、必ず現地確認ができる物件を選んでください。
例えば、営業担当者から高利回りで人気の物件と紹介されても、実際は建物が老朽化していたり、周辺の環境が悪かったりするケースもあるでしょう。
さらに、「入居率が高い」と言われても、近隣に競合する物件が多く空室リスクも高い地域であることが考えられます。実際に物件を確認することで、建物の状態や周辺環境、交通の利便性、近隣の治安などを自分の目で確かめられます。
また、管理状態が適切かどうか、共用部分の清掃が行き届いているかもチェックできるため安心です。営業担当者が「現地を見なくても問題ない」と説明する場合は、不動産の購入を避けたほうがよいでしょう。
担当者の言葉を安易に信じるのではなく、自ら確認する姿勢を持つことで投資のリスクを最小限に抑えられます。
参考:国民生活センター | 強引でしつこい投資用マンションの販売勧誘、どうすればいいの?(消費者トラブル解説集)
信頼できる不動産投資会社を選ぶコツ
不動産会社の誇大広告や強引な勧誘、リスクを隠した説明などに騙されないためには、慎重に会社を選ぶ必要があります。
信頼できる不動産投資会社を選ぶためのポイントを詳しく見ていきましょう。
ネット上の口コミや評判を確認する
不動産投資会社を選ぶ際は、まずネット上の口コミや評判を確認してみてください。
現在、多くの不動産会社がウェブサイトやSNSを運営しており、実際に利用した投資家のレビューを簡単に調べられます。口コミを見ることで、その会社の対応の良し悪しや、過去にトラブルがなかったかを把握できます。
ただし、口コミや評判はあくまで個人的な意見であり、すべてを鵜呑みにするのは危険です。例えば、不動産会社にとって不利な情報を意図的に拡散するケースや、逆に自社の評価を高めるためにサクラレビューを投稿している可能性もあります。
そのため、1つのサイトを見て判断するのではなく、複数の情報源をチェックすることが大切です。
宅地建物取引業の免許があるか確認する
不動産投資会社を選ぶときは、宅地建物取引業の免許を取得しているかを必ず確認してください。
宅地建物取引業の免許は、不動産の売買や賃貸の仲介、管理業務などを行うために必要な資格であり、無免許の会社は適法に営業できません。
宅地建物取引業の免許は、国土交通大臣または都道府県知事から取得するものです。宅地建物取引業の免許は一度取得をすれば永久的に有効というわけではなく、5年ごとに更新が定められています。
免許の更新がされていない場合、その会社は適正な業務を行っていない可能性があるため注意が必要です。
また、免許番号には「(1)」や「(3)」といった数字がついており、免許の更新回数を示しています。「東京都知事(3)第〇〇〇〇号」と記載されていた場合、その会社は11年以上15年未満の営業実績があることになります。
ただし、( )内の数字は、会社の法人化や営業所の新設などによって(1)に戻る場合もあるため、数字だけで会社の信頼性を判断するのは避けましょう。
投資するリスクを正直に話してくれるか
信頼できる不動産投資会社を選ぶときは、リスクについて正直に話してくれるかどうかを確認してください。
不動産投資は空室リスクや修繕費の負担、金利上昇によるローン返済額の増加など、さまざまなリスクを伴います。
悪質な業者や営業担当者は、「絶対に損をしない」「空室はほとんどない」「利回りはずっと安定している」など、メリットだけを強調してリスクについてはほとんど触れないことがあります。
しかし、不動産投資は市場の変動や経済状況の影響を受けるため、長期的に利益が保証されているものではありません。信頼できる会社であれば、物件のデメリットや想定されるリスクについてもしっかりと説明し、適切な対策を提案してくれるでしょう。
投資に関する不安や疑問に対して、曖昧な回答ではなく根拠のある情報を提供する会社であれば、安心して取引を進められます。
あなたのマンション・アパートの価格が分かる